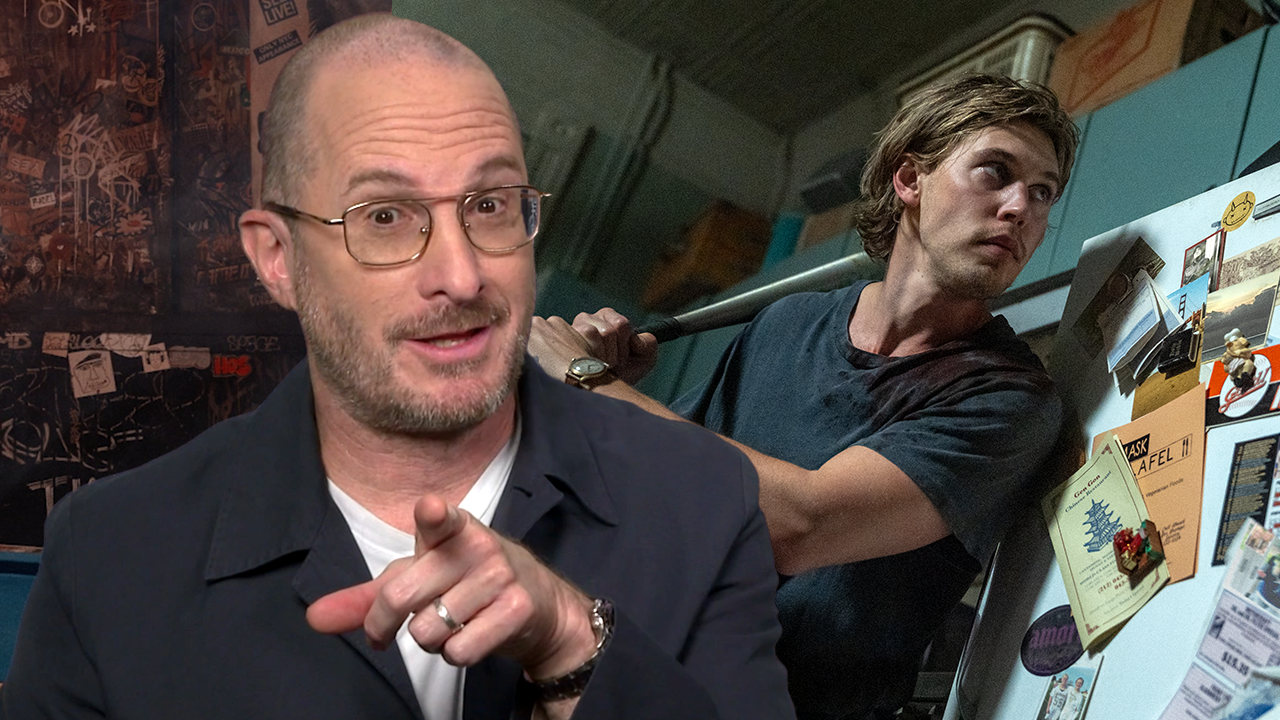来月から霞が関で除染土再生利用 政府がロードマップ正式決定
東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染で取り除かれた土の再生利用と福島県外での最終処分について、政府は26日、今後5年程度で取り組むロードマップを正式決定しました。
原発事故のあと、福島県内の除染によって取り除かれた大量の土などは、県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められています。
政府は、この最終処分の量を減らすため、放射性物質の濃度が低い土については全国の公共工事の盛り土などで再生利用する方針で、7月には福島県での実証事業を除いて全国で初めて総理大臣官邸の敷地内で再生利用しました。
政府は26日の会議で今後5年程度で取り組むロードマップを示し、再生利用については、9月から霞が関の中央省庁の花壇などで始めたうえで、地方の出先機関などでも検討するとしています。
また、最終処分については、2030年ごろに県外の候補地の選定や調査を始めるとし、ことし秋ごろには新たな有識者会議を設置することが盛り込まれました。
新たなロードマップは26日に正式決定され、浅尾環境大臣は会見で「再生利用における政府が率先した先行事例の創出や県外最終処分の検討および国民への理解醸成などの取り組みを着実に実行し、2045年3月までの県外最終処分の実現に向けて、引き続き政府一丸となって全力で取り組んでいく」と述べました。
林官房長官 “政府一丸で着実に前進を”
林官房長官は、「福島の復興に向けて中間貯蔵施設に保管されている除去土壌や指定廃棄物について、30年以内に県外での最終処分を実現するよう政府一丸となって着実に取り組みを前進させていくことが必要だ」と述べました。
そのうえで、「復興再生利用などの推進にあたっては、その必要性・安全性などに対する国民の幅広い理解醸成が重要だ。ポスターやSNSなどを通じた情報発信だけでなく、霞が関の中央官庁などを理解醸成に積極的に活用するようお願いしたい」と述べました。
専門家 “全国的理解や若い世代の理解が重要”

ロードマップが正式決定されたことについて、福島県の復興に詳しい東京大学大学院の開沼博准教授は、「本来であれば、もっと早く具体的な道筋が示され最終処分までの道筋が分かるのではないかと期待していた人は多かったと思う。2045年までに福島県外での最終処分を実現するためには、全国的な理解や若い世代の理解が重要であり、今から2030年までに理解の底上げを図り合意形成をどう進めるのか具体的につめていく必要がある」と指摘しています。
その上で、「この問題が解決しないと、被災で大変な思いをした現地の大熊町、双葉町が負担し続けるということになる。問題が解決されずに14年前から現在に続いていることを多くの人が共有することから始めてほしい」と話しています。