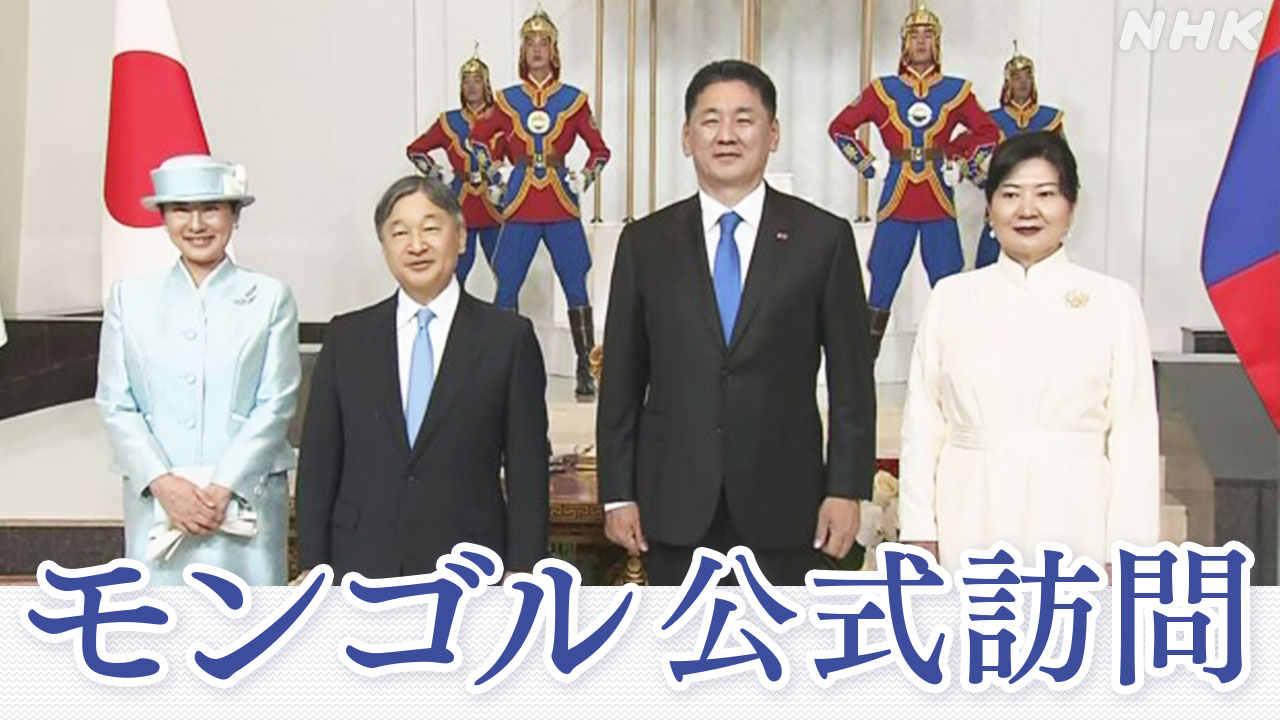生活保護の判決受け 厚労省が初の専門家会議 対応取りまとめへ
国が生活保護の支給額を段階的に引き下げたことを違法だとした最高裁判所の判決を受けて厚生労働省は13日、専門家による初めての会議を開きました。原告から減額された分の支給などを求める声が上がる中、国は今後複数回、会議を開き、国としての対応を取りまとめる方針です。
生活保護費をめぐって厚生労働省が、支給の基準に物価の下落を反映するなどとして2013年から3年にわたって支給額を段階的に最大で10%引き下げたことについて、最高裁判所はことし6月、当時の判断は違法だったとして、引き下げの処分を取り消す判決を言い渡し、国の敗訴が確定しました。
この判決を受けて、厚生労働省は、国としての対応を検討するため法律や福祉、それに経済学の専門家による委員会を設置し、13日、初めて会議を開きました。
会議では、引き下げに至った判断の「過程や手続き」に誤りがあったとした判決の内容について厚生労働省の担当者が説明し、今後、議論を進めるために必要な資料などについて委員から意見を聞きました。
引き下げが行われた当時の受給者はおよそ200万人とされ、裁判の原告や弁護団からは減額された分の支給や国からの謝罪など、早期の解決を求める声があがっていて国の対応が注目されています。
厚生労働省は2回目の会議を8月下旬に開く方針で、今後、原告からのヒアリングを行うことも検討しているということです。
【国の専門委員会 これまでの経緯や今後の焦点は】
生活保護の最高裁判所の判決を受けて新たに始まった国の専門委員会。
これまでの経緯や、今後、何が焦点となるのかをまとめました。
Q.最高裁判所の判決はどのような内容?
A.生活保護のうち食費や光熱費などの生活費にあてる「生活扶助」は、保護を受ける人の年齢や世帯の人数、暮らしている地域などに基づいて基準額が定められています。
この基準額は5年に1度、専門家で作る厚生労働省の部会で一般の所得が低い世帯の生活にかかる費用と比較するなどして検証され、その報告を受けた厚生労働大臣が最終的に決定します。
ことし6月の最高裁判所の判決では、2013年から2015年にかけて生活扶助の基準額を段階的に引き下げたことについて「厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱またはその乱用があり、違法だ」とし、この引き下げの処分を取り消す判決を言い渡しました。
Q.なぜ違法とされたのか?
A.判決では、基準額を引き下げるに至った厚生労働大臣の判断の「過程や手続き」に誤りがあったとしています。
引き下げは、
▽当時の物価の下落を踏まえた「デフレ調整」としておよそ580億円
▽専門家による部会が消費の実態に基づき検証した結果を踏まえた「ゆがみ調整」としておよそ90億円をそれぞれ削減するという内容でした。
このうち、「デフレ調整」には、厚生労働省が物価の動向をもとに算出した独自の指数が初めて使われましたが、そもそも基準額の指標に物価を使うことなどについて、専門家の部会では議論されませんでした。
こうした厚生労働大臣の判断の過程や手続きについて最高裁判所は、「専門的な知識に基づく説明が必要だが、国が十分説明したということはできない」と指摘し、「デフレ調整」は違法だと判断して国の敗訴が確定しました。
一方で、「ゆがみ調整」については不合理ではないとしたほか、原告が求めていた国による賠償については訴えを退けました。
Q.判決後にどのような対応がなされた?
A.判決後、原告や弁護団は厚生労働省を訪れて国による謝罪や引き下げの取り消しによる差額の支給などを求めました。
一方で、厚生労働省は、専門家による会議を新たに設け、判決の趣旨や内容を踏まえた今後の対応のあり方を審議する方針を後日、記者会見で示しました。
この対応について、原告らは、「謝罪さえ行わず、当事者である自分たちとの実質的な話し合いを拒否し続けている。当事者を軽視し、あまりにも不誠実だ」として、会議を設置するという方針を撤回するとともに、早期の全面解決を図るよう改めて求めていました。
このほか、原告らは国に対し、再発防止のため、2013年の改定が行われた具体的な事実経過や原因などについて、調査や検証を行うことも必要だと訴えています。
Q.今後の焦点は?
A.最高裁判所の判決では、「デフレ調整」に関する厚生労働大臣の判断の過程や手続きに誤りがあったとされていますが、
▽そもそも物価の動向を基準額の指標とすることや
▽判決で不合理ではないとされた「ゆがみ調整」の内容を含めて検討するべきかなど、議論の論点をどのように整理するかが焦点となります。
その上で、仮に補償を行うとした場合、誰に対して、どれくらいの金額をどのように支給するかということも決める必要があります。
生活扶助は年齢や世帯の人数、暮らしている地域などに応じて異なるほか、収入がある場合はその分が差し引かれるので、受給している人ごとに金額は異なります。
当時の受給者はおよそ200万人いるとされ、最初の引き下げから10年以上がたつ中で、正確な補償額を調べるには、膨大な作業が必要になると専門家などが指摘しています。
そして、判決後に原告が求めている謝罪や当時の検証などに対し、国が今後どう対応するかについても注目されます。