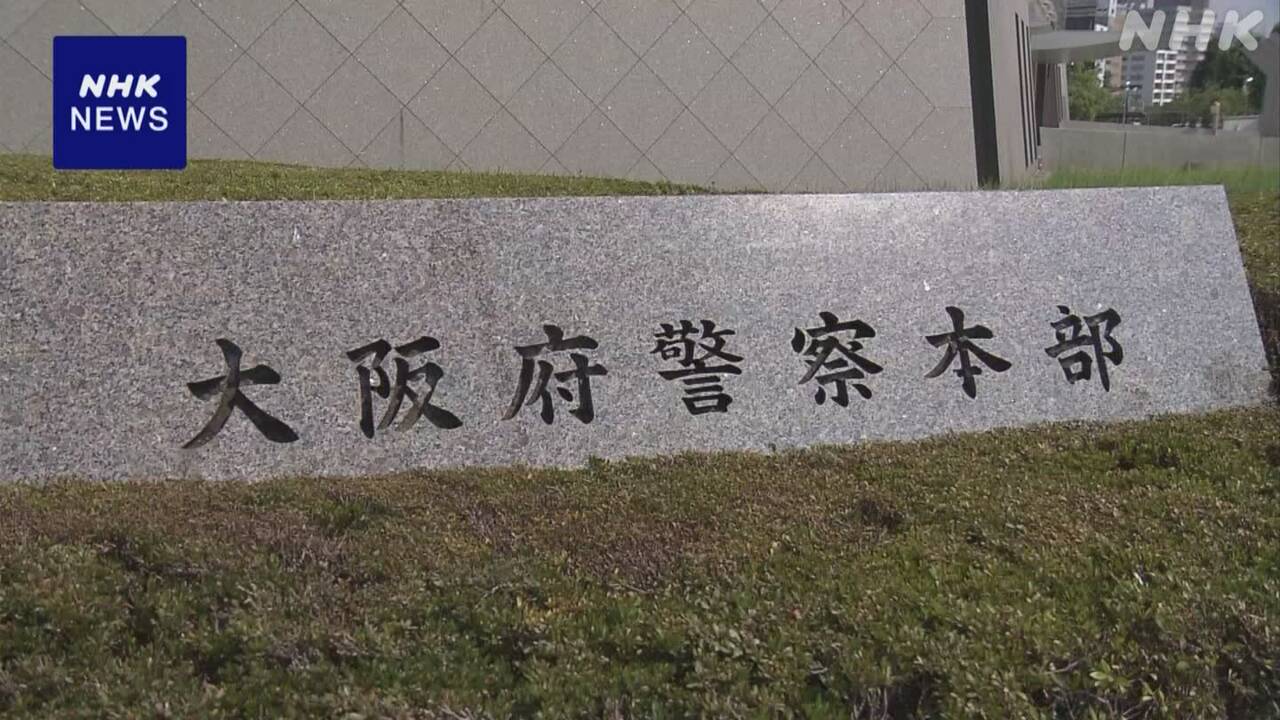活発な噴火活動が続く霧島連山の新燃岳で、噴煙が5000メートルまで上がる噴火が起きてから、10日で1週間です。最新の研究で、地下のマグマの影響が強まっている可能性も示され、気象台は引き続き警戒するよう呼びかけています。
霧島連山の新燃岳では、6月22日に2018年6月以来となる噴火が発生し、その5日後の27日から観測している噴火が現在も続いています。
この噴火活動で1週間前の7月3日の午後には、噴煙が火口から5000メートルまで上がりました。
火山ガスに含まれる二酸化硫黄の放出量も6月23日に1日あたり4000トンと急激に増加し、3日前の7日の観測でも900トンとやや多くなりました。
また衛星による観測で地下深部の膨張を示すわずかな変化も見られるなど、気象台は火山活動が活発な状態で経過しているとしています。
さらに、産業技術総合研究所が7月2日の噴火の火山灰を分析した結果、新しいマグマに由来する物質が噴火が始まった当初よりも増えていることが分かり、気象台はこれまでより地下のマグマの影響が強くなっている可能性を示しているとしています。
気象台は今後、本格的なマグマ噴火に移行すると、大量の降灰や溶岩流の発生などを伴う噴火が想定されるとしていて、噴火警戒レベル3の火口周辺警報を継続して、火口からおおむね3キロの範囲では噴火に伴う大きな噴石に、おおむね2キロの範囲では火砕流に警戒するよう呼びかけています。
また、爆発的な噴火に伴う「空振」=空気の振動で窓ガラスが割れるおそれもあるとして、注意を呼びかけています。