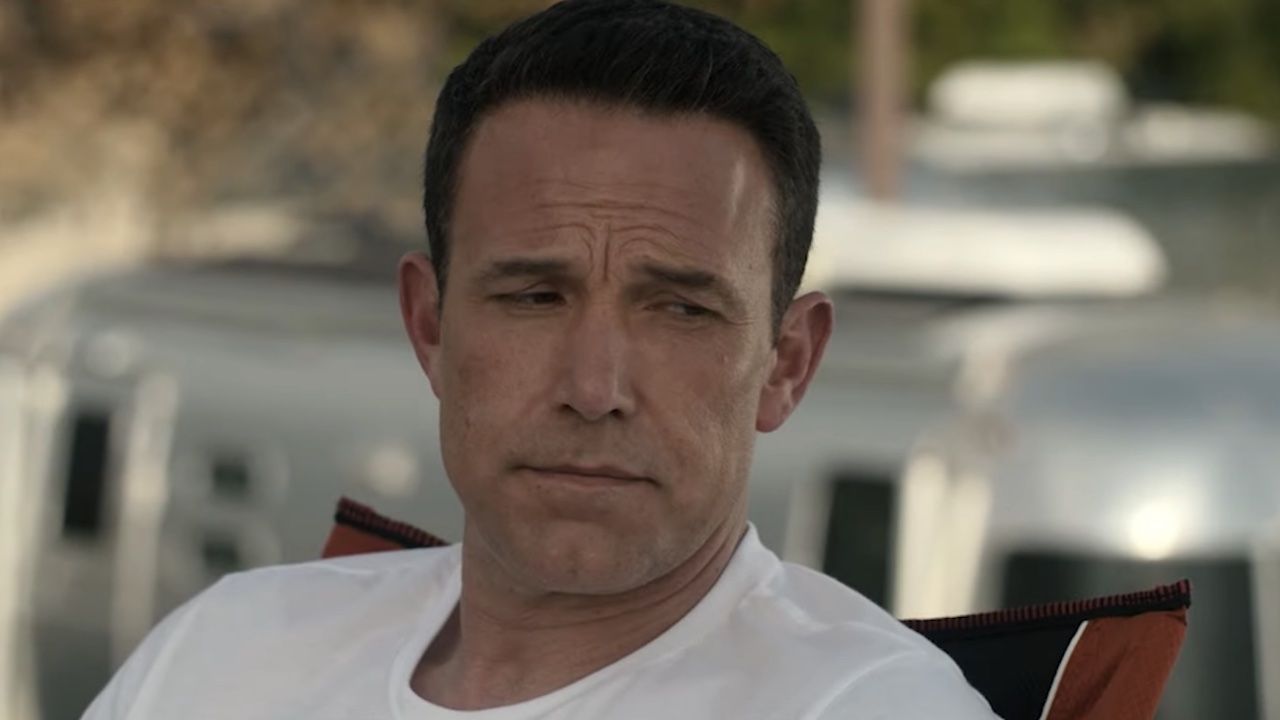福井県 沖合で死んだイルカ 海水浴客をけがさせたイルカと断定
13日、福井県敦賀市の沖合で野生のイルカが死んでいるのが見つかりました。県は、取り付けた発信機があったことなどから、海水浴客をかんでけがをさせていたイルカと断定し死因を詳しく調べています。

福井県などによりますと県内の海水浴場では、泳いでいた人などが野生のイルカにかまれてけがをする被害が3年前から相次ぎ、去年までにあわせて52人がけがをしました。
これを受けて県はことし6月、国に許可を取ったうえで、人に危害を加えていたとみられるイルカに発信機を取り付けましたが、先月1日を最後に記録が途絶えていました。
こうした中、13日正午ごろ、福井県敦賀市の沖合で、野生のイルカが死んで浮いているのを漁業関係者が見つけて漁協を通じて県に連絡しました。
県水産試験場の職員が調べたところ、背びれには、県が取り付けた発信機が付いていて、体の傷や尾びれなどの特徴から海水浴客をかんでけがをさせていたイルカだと断定したということです。
県は、イルカの死因を詳しく調べています。