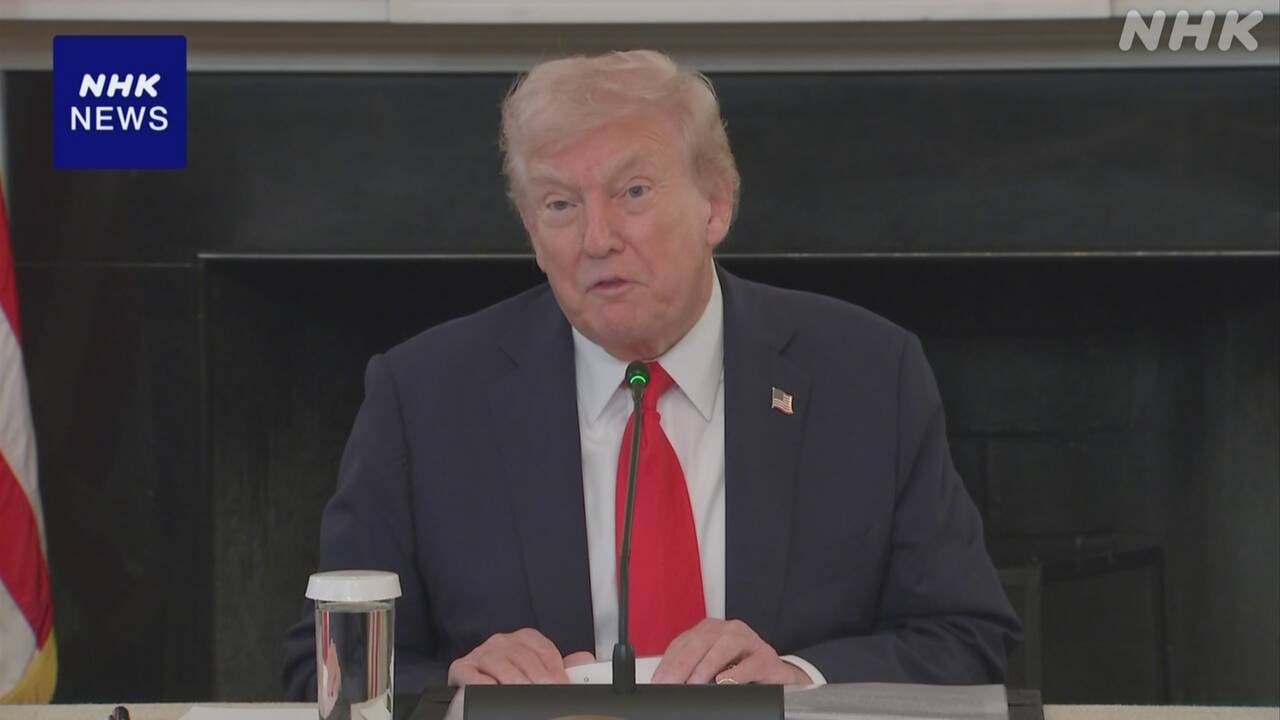介護と障害福祉 同じ場で提供「共生型サービス」促進を 検討会
2040年には65歳以上の高齢者の数がほぼピークになると推計され、介護サービスの維持や人材の確保が課題となる中、厚生労働省の検討会は介護と障害福祉を同じ場所で提供する「共生型サービス」など、限られた人材を有効に活用する体制作りが重要だととりまとめ、審議会に報告することになりました。
厚生労働省の有識者による検討会は、65歳以上の高齢者が3928万人とほぼピークになると推計される2040年に向けて、介護などの福祉サービスの提供体制について検討を進めてきました。
24日、検討会のとりまとめ案が示され、すでに介護職員の数が減少に転じるなどサービスの維持や人材の確保などが課題となる中、同じ事業所で介護と障害福祉を提供する「共生型サービス」という分野を超えた連携を促進することなどの方向性が了承されました。
共生型サービスでは介護と障害福祉の分野を超えてスタッフを柔軟に活用でき、人材確保が難しい地域でのサービス維持に有効だとしています。
厚生労働省は今回のとりまとめを今後、専門家による審議会に報告し、具体的な支援策について、必要な法改正などを議論する方針です。
「共生型サービス」とは
「共生型サービス」とは介護と障害福祉の両方を提供しているサービスのことで、2018年に制度が設けられました。
障害者が65歳以上になると、障害福祉よりも介護が優先され、一般的にはこれまでサービスを受けていた障害福祉の事業所から、介護サービスを提供している別の事業所に移行することになります。
「共生型サービス」の指定を受けた事業所であれば、障害者が65歳以上になっても同じ事業所でサービスが受けられるほか、地域にとっても限られた人材をサービスの需要に合わせて介護と障害福祉の両方で活用することが可能になります。
「共生型サービス」は介護と障害福祉両方の専門的な対応が求められるほか、それぞれで報酬を請求する必要があるため事務手続きが煩雑だといった声もあります。
さらに、取り組み状況に地域で差が生じていることが課題にあがっていて、「共生型サービス」の事業所数は去年10月時点で都道府県別に、最も多い大阪府はのべ153事業所である一方、石川県と徳島県はそれぞれのべ5事業所で、ばらつきが出ています。