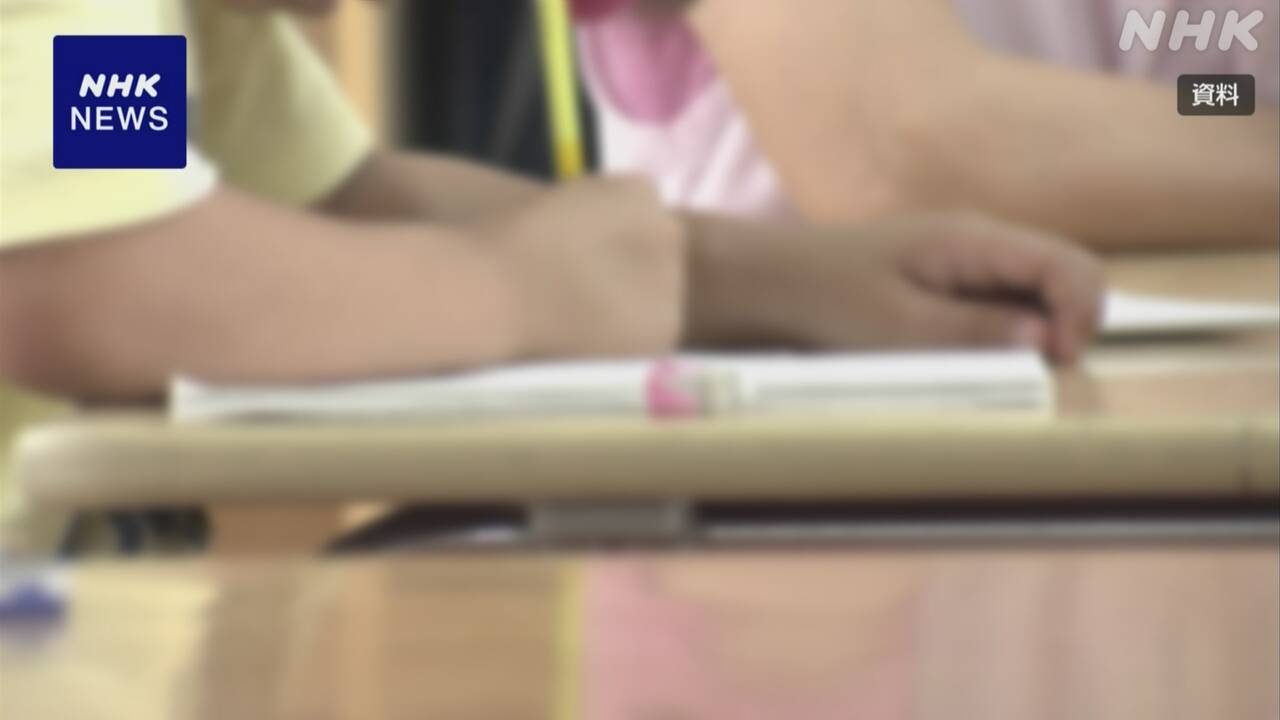共働き家庭などの小学生を放課後に預かる「学童保育」。定員に空きがないなどの理由で利用できない待機児童の数は去年、過去2番目の多さとなっていましたが、最も多かった東京都のうち23区の最新の状況を調べたところ、今年度は1800人余りと、8年ぶりに2000人を下回ったことがわかりました。
小学生が放課後の時間を過ごす「学童保育」は共働き家庭の増加などで利用のニーズが増えていて、定員に空きがないなどの理由で利用できない待機児童の数は去年、全国で1万7600人余りと、過去2番目に多くなりました。
こうした中、最も多かった東京都のうち23区の最新の状況を調べたところ、ことし5月時点の待機児童の数は1841人と前の年から443人減少し、平成29年以来、8年ぶりに2000人を下回ったことがわかりました。
自治体別にみると
▽杉並区が481人
▽中央区が275人
▽目黒区が246人
▽葛飾区が4月時点の速報値で243人
▽足立区が179人
▽大田区が155人などとなっています。
待機児童はいないと回答した自治体も10ありました。
一方で、1年生から3年生までの低学年の利用を優先する自治体の中には、4年生以上の申し込みを受け付けず、そもそも待機児童としてカウントしていないケースもありました。
学童保育の問題に詳しい新潟県立大学の植木信一 教授は「国の学童保育への支援も手厚くなり、自治体が学童保育を作る際の整備費の補助率がかさ上げされるなど仕組みが活用されてきている。補助制度の活用は各自治体に任されているので、そのあたりの普及が今後の課題だ」と話しています。