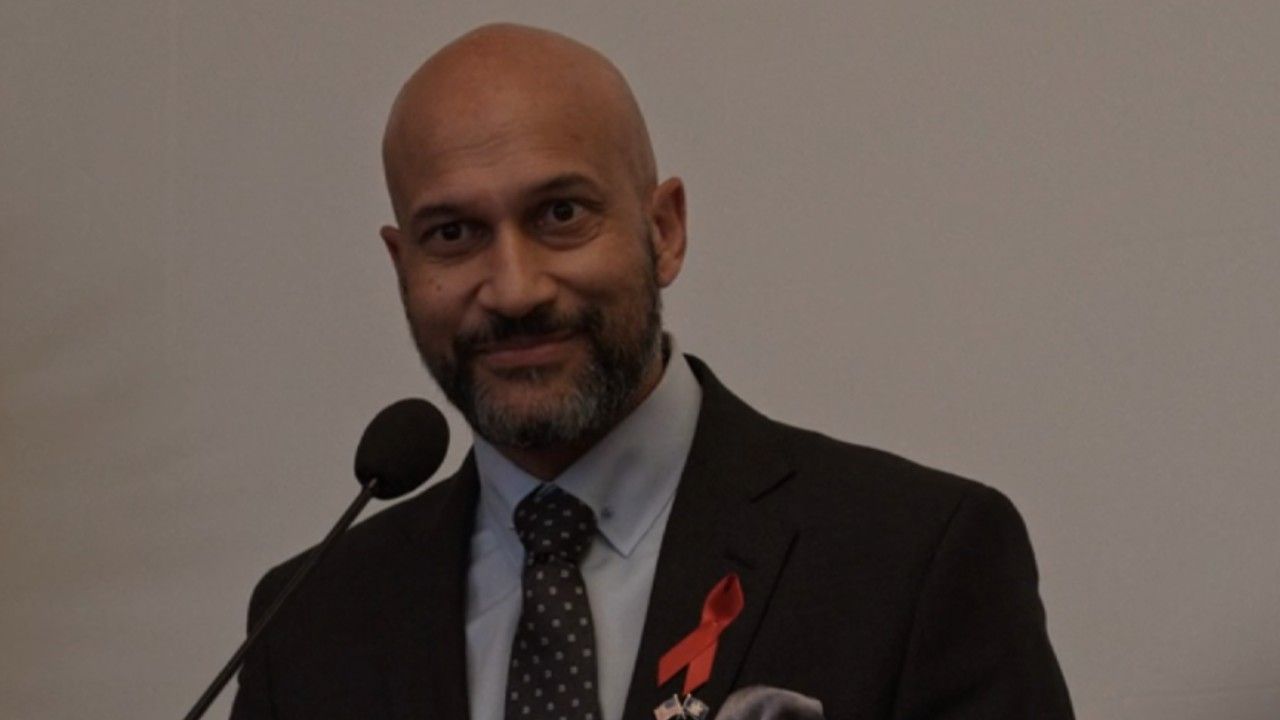多くの登山者が犠牲となった御嶽山の噴火から27日で11年です。
当時、「噴火警戒レベル」が最も低い「1」の状態で突然、噴火が起きましたが、その後も、全国の火山ではレベル「1」での噴火が複数発生し、なかには活動の高まりが登山者に十分に伝わっていない可能性がある事例もありました。
専門家は、情報の伝え方などを改めて確認する必要があると指摘しています。
御嶽山噴火から11年 追悼式で犠牲者に祈り 戦後最悪の火山災害
ふもとの長野県王滝村では追悼式が行われ、遺族などが噴火が起きた時刻に合わせて犠牲者に祈りをささげました。

2014年9月に起きた御嶽山の噴火では、噴火警戒レベルが最も低い「1」の状態で噴火が発生して登山者が巻き込まれ、多くの犠牲者が出ました。
その後、観測が強化されていますが、気象庁によりますと気象庁が常時観測している火山では27日までの11年間に、噴火警戒レベルが「1」の状態で噴火が発生した事例が、群馬県の草津白根山や、長野と群馬の県境にある浅間山など、あわせて4事例あったということです。

このうち、北海道東部の雌阿寒岳では、レベル「1」だった今月12日、火山性微動や地殻変動などが観測されたあと噴気の量も増加するなど活動が高まりました。
3日後の15日に「火口周辺規制」を示すレベル「2」に引き上げられましたが、気象庁によりますと、レベルが上がるまでの間にごく小規模な噴火が発生していたということです。

周辺の自治体が火口近くの登山道を規制したり、火山活動の高まりを登山者に伝えたりしたのはレベルが引き上げられてからで、登山者用の地図アプリ「YAMAP」の運営会社によりますと、活動の高まりが観測された今月12日から15日までの間に火口近くにいたとみられる人の投稿が複数寄せられていたということです。

火山防災に詳しい東京大学の藤井敏嗣名誉教授は噴火警戒レベル「1」で火口近くに登山者などがいる場合は、小さな噴火でも災害につながる可能性があるため情報の発信や伝え方について改めて確認する必要があると指摘しています。
藤井名誉教授
「警戒レベルの引き上げの基準を満たしていなくても、人に危害を与える可能性があるような活動の高まりを見つけたら、気象庁は臨時の解説情報を出すなど、ふだんと違う現象が起きていると知らせるのが重要だ」
「臨時」の解説情報も発表されず
雌阿寒岳の火山活動は先月まで静穏に推移していましたが、今月中旬に入って高まりがみられました。
噴火警戒レベルが「1」だった今月11日からポンマチネシリ火口付近を震源とする地震がやや増加し、12日には火山性微動の発生に伴って火口方向が上がる傾斜変動も観測されました。
噴気の量も増加したことなどから、気象庁は火山活動の状況を知らせる解説情報を12日の夕方と夜など、複数回発表しました。
ただ、噴火警戒レベルを「2」に上げるのは15日の現地調査のあととなり、火口近くの登山道はそれまで通行が出来る状態でした。

また、レベルの引き上げには至らないものの、通常と異なる変化を伝える「臨時」の解説情報も発表されず、周辺の自治体が登山道に情報を掲示するなどして火山活動の高まりを登山者に伝えたのはレベルが引き上げられてからでした。
その後、火口周辺、最大300メートルの範囲に火山灰が積もっていたことが確認され、気象庁は今月22日になって、ごく小規模な噴火が発生していたと発表しました。
気象庁によりますと、噴火が発生したのは、レベルが上がる前の今月12日から15日までの間とみられるということです。
気象庁は噴火の規模はごく小さく、登山者に危険が及ぶものではなかったとする一方、現地で観測を行うまでレベルを「2」に引き上げられなかったのは改善点だとして、同じような活動が起きた場合でもレベルを引き上げられるよう基準の見直しを行うとしています。
火山活動高まった期間に登山の投稿も
登山者用の地図アプリ「YAMAP」の運営会社によりますと、雌阿寒岳では活動の高まりが観測された今月12日から15日までの間に火口近くまで登山したとみられる人の投稿が複数寄せられていたということです。
雌阿寒岳では今月15日に噴火警戒レベルが「2」に引き上げられるまで登山道は規制されておらず、火口近くの登山道も通行できる状態でした。
このうち、今月13日には山頂近くの火口内の様子を写した画像などとともに「噴煙に混じった灰が舞って顔にあたる」とか「全身に何かが当たって痛い」、「ジェット機のようなスゴイ音が響いています」などという投稿がされていました。
また、火山活動の高まりを下山後にニュースで知ったという投稿も見られました。
登山道の規制 地元自治体の対応は
北海道東部にある雌阿寒岳の登山道の規制は、噴火警戒レベルが「2」や「3」に引き上げられた際に行われることになっています。

今回も今月15日に噴火警戒レベルが「2」に引き上げられたあと、ふもとの釧路市や足寄町が火口周辺への立ち入りを規制しました。
一方で、レベルが上がるまで、登山道に情報を掲示するなど、自治体が活動の高まりを登山者に伝えることはありませんでした。
御嶽山噴火を教訓に 防災情報見直しも
御嶽山の噴火を教訓に、気象庁は火山の観測機器を増やすなど体制を強化するとともに、火山の防災情報も見直しました。
【“臨時”の解説情報】
御嶽山では噴火の2週間ほど前から火山性地震が増加していたため気象庁は「解説情報」で活動状況を発表していましたが登山者などに十分に伝わっておらず、噴火警戒レベルの引き上げには至らないものの、火山活動に通常と異なる変化があった場合は「臨時」と明記した解説情報を発表することになりました。
国は周辺の自治体に対して「臨時」の情報が発表された場合の具体的な対応についてあらかじめ検討しておくよう求めています。
【噴火速報の導入】
また、火口付近にいた多くの登山者が犠牲になったことを受けて、噴火したことをいち早く伝えるため「噴火速報」を導入しました。
【レベル1も活火山に留意】
さらに噴火警戒レベルについても、当時「レベル1」で「平常」という表現だったため、「安全だという誤解につながる」などといった意見があがり「活火山であることに留意」に表現が見直されました。
【観測機器や人員増で体制強化】
また、気象庁は火山活動の小さな変化を捉えようと全国の火山で観測機器を増やしました。その上で、データを分析したり現地で観測したりする職員の数を噴火前の2倍近いおよそ280人に増やすなど、体制を強化してきました。
新たな観測データや火山活動に関する知見が得られた場合などには、火山ごとに設定している噴火警戒レベルの判定基準を見直しています。
一方で、噴火に至るメカニズムは分かっていない点も多く、得られたデータの評価や、規模の小さな噴火の兆候を捉えることにはまだ課題があります。
気象庁は「引き続き、観測に努め、データをもとに適切に火山活動を評価していく。ただ、現状では噴火の前兆を完全に捉えるのは難しく、活火山に立ち入る際には、火口周辺に影響があるような噴火はいつ発生してもおかしくないと思って行動してほしい」としています。