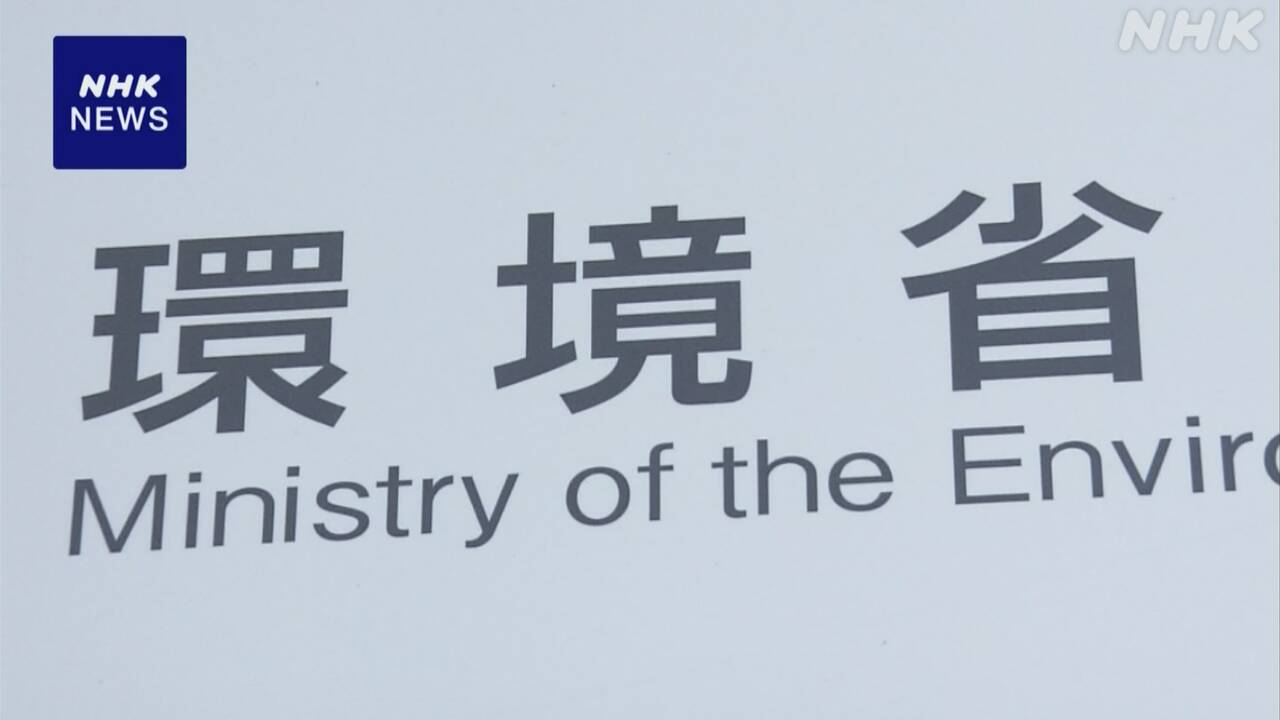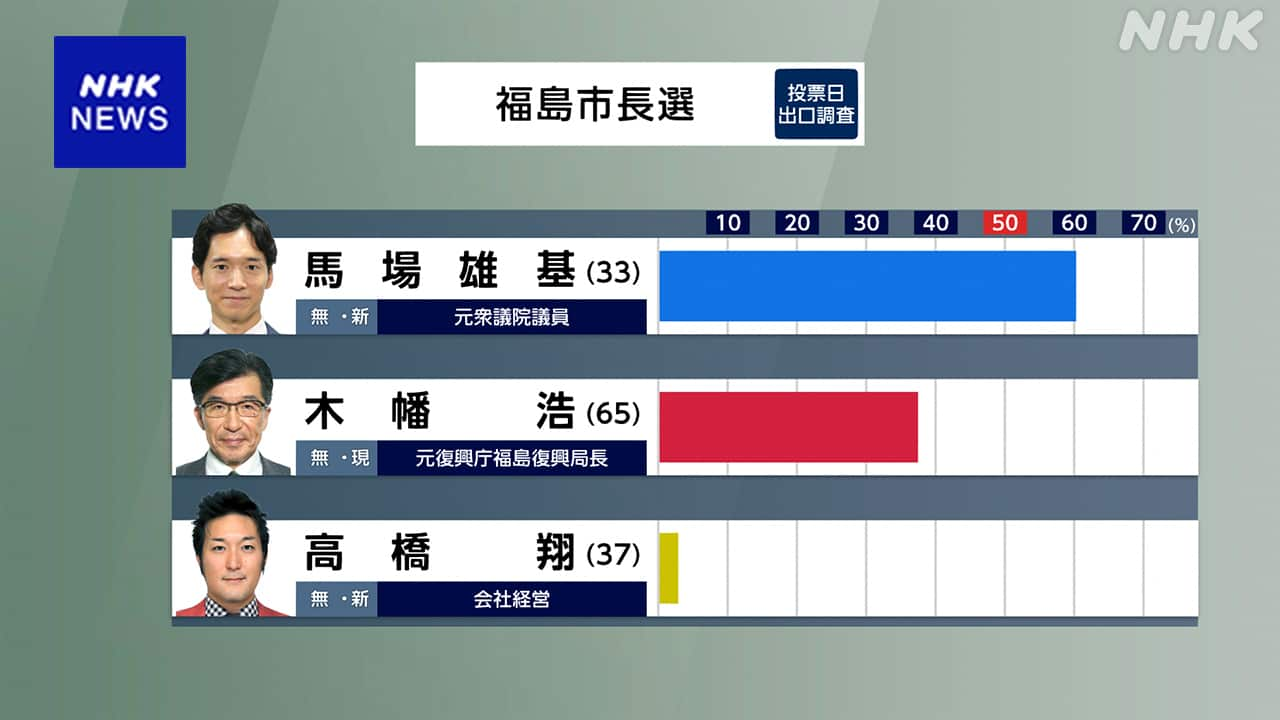希少昆虫などの標本 無償での個人間譲渡を許可へ 環境省
絶滅のおそれのある生物の保全を目的とした「種の保存法」で、譲渡が禁止されている希少な昆虫などの標本について、環境省は、個人が所有している標本を研究に活用できるよう、一定の条件のもと、個人間の無償での譲渡を許可する方針をまとめ、10月にも新たな運用を始めることになりました。
絶滅のおそれのある生物の保全を目的とした「種の保存法」で「国内希少野生動植物種」に指定された生物は、乱獲を防ぐため、原則、採集だけでなく、個人間の標本の譲渡も禁止されています。
しかし、アマチュアの研究者などが指定前から所有している標本は、所有者が高齢になるなどして管理できなくなっても、ほかの人に譲渡できず、廃棄せざるをえない状況になっていました。
環境省は、こうした標本を保存し研究に活用できるよう、昆虫などについては、無償であれば個人間での譲渡を許可するよう運用を見直す方針をまとめました。
譲渡できる標本は、
▽採集した日付や場所などの記録から指定前に採集されたことが確認できるものが対象で
▽専門の学会からの推薦が必要になるとしています。
環境省は、10月にも通知を出して、新たな運用を始めることにしています。
環境省野生生物課は「学術的な価値がある標本は、生物の保全という観点からも非常に重要で、適切に引き継がれていくよう運用していきたい」とコメントしています。
”今後の管理で悩み抱える高齢の愛好家も”

青森市に住む黒滝敏文さん(69)は、自身で採集するなどしたおよそ1万点のチョウの標本を自宅で保管しています。
特に「ゴマシジミ」という種に興味を持ち、採集地ごとの標本の、はねの模様の違いを統計的に調査して、アマチュアの研究者として学会で報告してきました。
しかし、「ゴマシジミ」は、長野県や山梨県などに分布する「関東・中部亜種」が2016年に「種の保存法」の国内希少野生動植物種に指定されました。
黒滝さんは、この亜種の標本をおよそ600点所有していますが、高齢になり、今後、管理が難しくなることを見越して、標本の寄贈を地元の博物館に相談したところ、受け入れは難しいと言われたということです。

黒滝さんは、今回の運用見直しについて「私たちの世代は、子どものころ、夏休みに昆虫標本を作るなどして興味を持ち、それから趣味にしている人が多いと思いますが、家族に標本を管理してくれというのも無理な話なので、同じ悩みを抱えている高齢の愛好家は多いと思います。標本に愛着もありますが、後世に残すことが一番大事なので、私よりも若くて、きちんと管理していただける方を探して預けたいと思います」と話していました。
博物館では 寄贈の希望も受け入れ難しい現状
「種の保存法」で指定されている希少な昆虫などの標本の譲渡は、これまでは博物館や研究機関に限って認められていました。
しかし、全国の博物館などでは、収蔵品を保管する場所の確保が課題となっていて、寄贈の希望があった標本を、すべて受け入れるのは難しいのが現状です。
およそ100万点の昆虫標本を所蔵している東京大学総合研究博物館の収蔵庫も、スペースがひっ迫しています。
通路には、棚におさまりきらない標本箱が積み重ねられていて、新たな標本の受け入れは、所蔵している数が少ない種に限っているということです。
東京大学総合研究博物館の矢後勝也講師は「かつて普通に生息していた昆虫が、どんどん減少して希少種として指定されるようになっている。特に、チョウなどは、アマチュアの研究者や愛好家が、指定前の標本を持っているケースが多いが、博物館などに受け入れる余力がなく、行き先がない状態だった。標本とは、ある地域にその種が生息していたことを示す証拠であり、後世に残すことは、博物館だけではなく研究者全体の使命だ。今回の運用見直しで、貴重な標本が、若い研究者にうまく引き継がれるようになってほしい。一方で、標本の管理を個人だけに任せるのではなく、公的な研究機関や、博物館の収蔵スペースの確保も必要だ」と話していました。