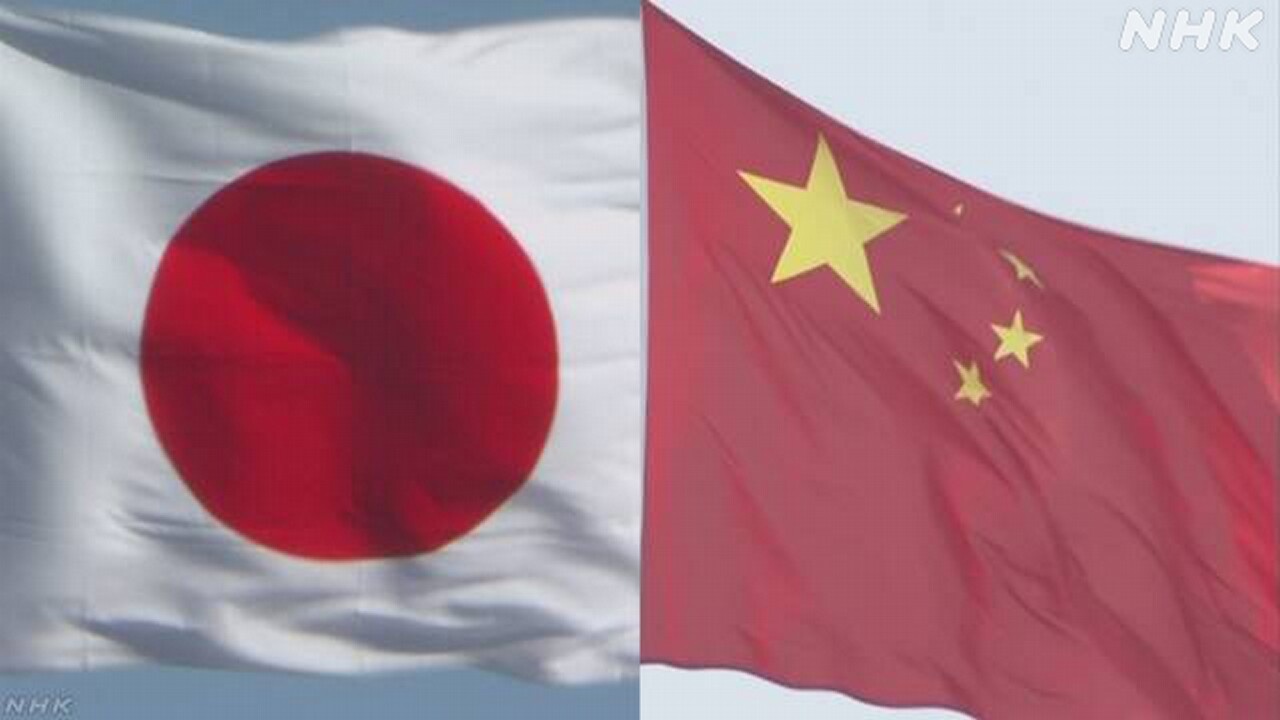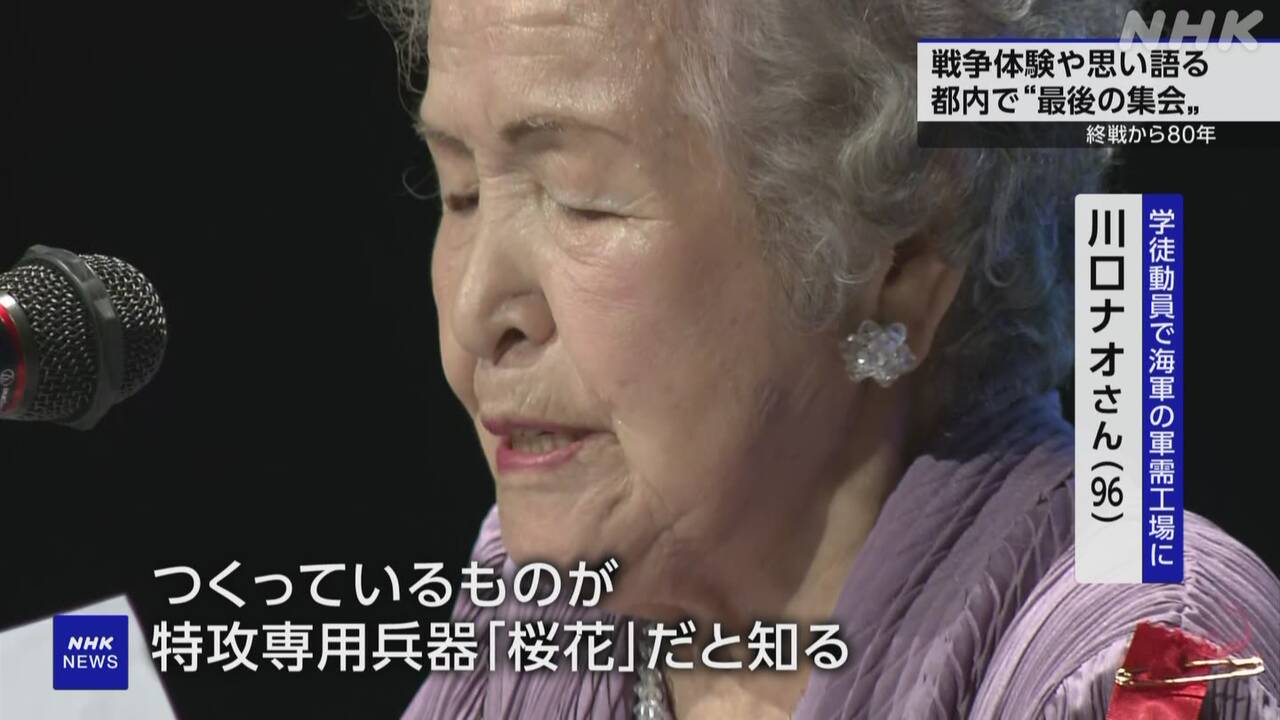日本政府 “中国の日本産牛肉輸入再開に必要な協定が発効”
中国が20年以上前から続けている日本産牛肉の輸入停止措置をめぐり、日本政府は、輸入の再開に必要な協定が7月11日に発効したと発表しました。両政府は、今後、輸入再開に向けた具体的な協議を進めることにしています。
日本で牛の病気「BSE」が発生したことを受けて、中国は2001年から、日本産牛肉の輸入停止措置を続けていて、日本政府は、国内の畜産事業者の要望なども踏まえ、中国側に措置の撤廃を働きかけてきました。
こうした中、日本政府は、2019年に、輸入再開に向けた手続きを進めるために両国間で署名したものの、発効していなかった協定が、中国側の手続きが完了したことを受けて、11日発効したと発表しました。
協定は、畜産物の安全な取引を促進するため検疫に関する協力などを定めたものです。
今後、両国の関係省庁が牛肉の安全性を評価する仕組みづくりや、衛生面での基準の設定など、輸入再開に向けた具体的な協議を進めることになります。
日本産食品の輸出入をめぐっては、中国が6月、東京電力福島第一原発にたまる処理水の海洋放出を受けて、おととしから停止していた日本産水産物の輸入について、福島県や宮城県、東京都など10都県を除き、再開すると発表していました。
自民 森山幹事長「1つの前進を見ることができた」

中国による日本産牛肉の輸入停止措置をめぐり、日中友好議員連盟の会長を務める自民党の森山幹事長は、中国政府が、輸入の再開に必要な協定を発効したことを明らかにしました。
超党派の日中友好議員連盟の会長を務める自民党の森山幹事長は、大阪・関西万博のナショナルデーの式典にあわせて日本を訪れている中国の何立峰副首相と、11日午前、会場内でおよそ30分会談しました。
この中で、両氏は、2001年に、牛の病気「BSE」が日本で発生したことを受けて、中国が日本産牛肉の輸入を停止している措置をめぐり意見を交わしました。
このあと、森山氏は大阪市内で開かれた会合であいさつし「何副首相と会談し、長年の懸案であった牛肉の輸出問題について1つの前進を見ることができた。中国政府がきょう協定を発効したので具体的に話が進むと思う。24年ぶりに中国への牛肉の輸出が始まることにつながる」と述べました。
牛肉の中国輸出めぐる経緯
中国は、日本で牛の病気「BSE」が発生したことを受け、今から24年前の2001年から日本産牛肉の輸入を停止しています。
2019年になって、日本はBSEなど動物の病気の対策や検疫の分野で協力を強化する協定を中国と結び、日本からの牛肉輸出が再開されると期待されていました。
ところが、中国側が協定発効の手続きを進めないため、協定を結んだあともなお再開できない状態が続いていました。
一方、日本産の牛肉は、霜降りを特徴とする日本固有の「和牛」の品質が海外で評価され、年を追うごとにニーズが増しています。
輸出の拡大を目指す日本側の要請に基づいて、2013年にEU=ヨーロッパ連合、2017年に台湾、それに2020年にサウジアラビア向けの輸出が解禁されました。
農林水産省によりますと、2024年1年間の牛肉の輸出額は648億円と、比較可能な3年前の2022年と比べて20%以上増えています。
政府は、牛肉の輸出額を2030年に1132億円まで増やす目標を掲げていて、畜産業界では、巨大市場である中国への輸出再開に改めて期待が高まっています。
和牛の輸出企業から期待の声

滋賀県特産の和牛「近江牛」を扱う企業からは期待の声が上がっています。
滋賀県竜王町の企業では、アメリカやシンガポール、タイなどに近江牛を輸出していますが、特に品質の高い部位の需要が年々高まり、売り上げが伸びているということです。
オカキブラザーズフーズの岡山和弘社長は「明るいニュースとして受け止めている。中国への輸出が解禁される可能性があるなら探っていきたい」と話していました。
その一方で、牛肉価格の先行きについては懸念を示しました。
岡山社長は「中国は人口も多いので引き合いもかなりあると予測される。一気に和牛の需要が高まると、日本の牛肉価格も上がるおそれがあり、その点はすごく心配している」と話していました。