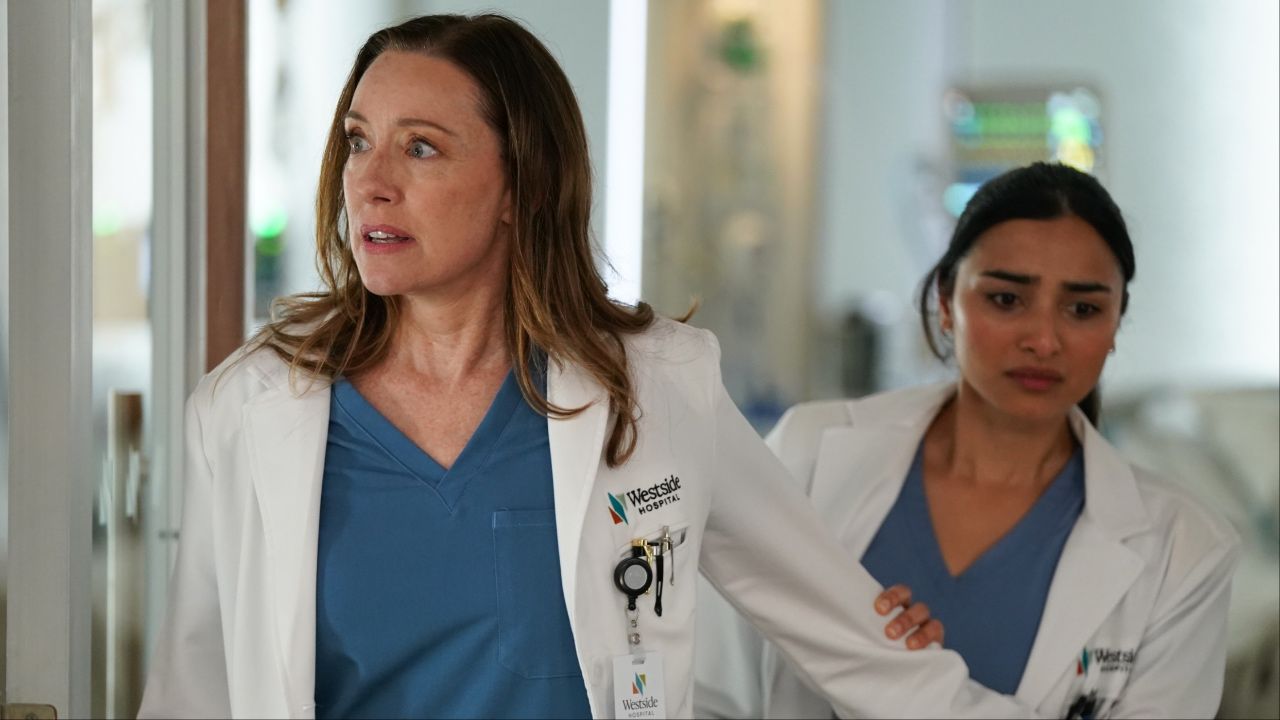広島への原爆投下から、6日で80年です。平和記念式典の平和宣言で広島市の松井市長は「『自国を守るためには、核兵器の保有もやむを得ない』という考え方が各国で強まりつつある事態は、過去の悲惨な歴史から得た教訓を無にするものだ」と述べたうえで、核兵器廃絶への思いを市民社会の総意にするよう訴えました。
広島市の平和公園で午前8時から行われた平和記念式典には、被爆者や遺族の代表をはじめ、石破総理大臣のほか、過去最多となる120の国と地域の大使などを含むおよそ5万5000人が参列しました。
式典では、広島で被爆し、この1年に亡くなった人や死亡が確認された人、あわせて4940人の名前が書き加えられた34万9246人の原爆死没者名簿が、原爆慰霊碑に納められました。
そして、原爆が投下された午前8時15分に、参列者全員が黙とうをささげました。
国際社会では、核保有国による威嚇が繰り返されたり、核抑止力を強化しようとする動きがみられたりするなど、核兵器をめぐる情勢は厳しさを増しています。
広島市の松井市長は平和宣言で「世界中で軍備増強の動きが加速し、各国の為政者の中では、『自国を守るためには、核兵器の保有もやむを得ない』という考え方が強まりつつあるが、こうした事態は、国際社会が過去の悲惨な歴史から得た教訓を無にすると同時に、これまで築き上げてきた平和構築のための枠組みを大きく揺るがすものだ」と述べて懸念を示しました。
そして「核兵器廃絶への思いを市民社会の総意にしていかなければならない。被爆者をはじめ、先人がつくりあげた『平和文化』が国境を越えて広がっていけば、必ずや核抑止力に依存する為政者の政策転換を促すことになる」と訴えたうえで、日本政府に対し、来年行われる核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加するよう求めました。
石破総理大臣はあいさつで「非核三原則を堅持しながら、『核兵器のない世界』に向けた国際社会の取り組みを主導することは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命だ」と述べましたが、核兵器禁止条約にはふれませんでした。
また、地元の小学生2人は「本当はつらくて思い出したくない記憶を伝えてくださる被爆者の方々から、直接話を聞く機会は少なくなっています。被爆者の声を次の世代へ語り継いでいく使命が、私たちにはあります」と、「平和への誓い」を述べました。
被爆者の平均年齢はことし86歳を超え、初めて10万人を下回り、被爆体験を直接聞くことは次第に難しくなってきています。
人類史上初めて核兵器の惨禍を経験した広島は、犠牲者を追悼するとともに、被爆者たちが一貫して繰り返してきた核兵器廃絶の声を改めて国内外に強く訴えます。
石破首相 “「核兵器のない世界」実現へ全力”
石破総理大臣は、平和記念式典であいさつし「80年前のきょう、1発の原子爆弾がさく裂し、十数万とも言われる貴い命が失われ、一命をとりとめた方々にも筆舌に尽くし難い苦難の日々をもたらした。惨禍を決して繰り返してはならない」と述べました。
その上で、非核三原則を堅持しながら国際社会の取り組みを主導することは、唯一の戦争被爆国である日本の使命だと強調しました。
そして、イランの核開発をめぐる中東情勢などを念頭に「核軍縮をめぐる国際社会の分断は深まり、安全保障環境は厳しさを増している。NPT=核拡散防止条約のもと『核戦争のない世界』そして『核兵器のない世界』の実現に向け、全力で取り組んでいく」と述べました。
また、去年、日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞したことは極めて意義深いとした上で「被爆者の平均年齢は86歳を超え、国民の多くは戦争を知らない世代となった。耐え難い経験と記憶を決して風化させることなく、世代を超えて継承しなければならない」と訴えました。
さらに「被爆者援護法」の施行から30年となったことを踏まえ、原爆症の認定についてできるかぎり迅速な審査を行うなど、高齢化が進む被爆者に寄り添いながら、総合的な援護施策を進めていく考えを示しました。