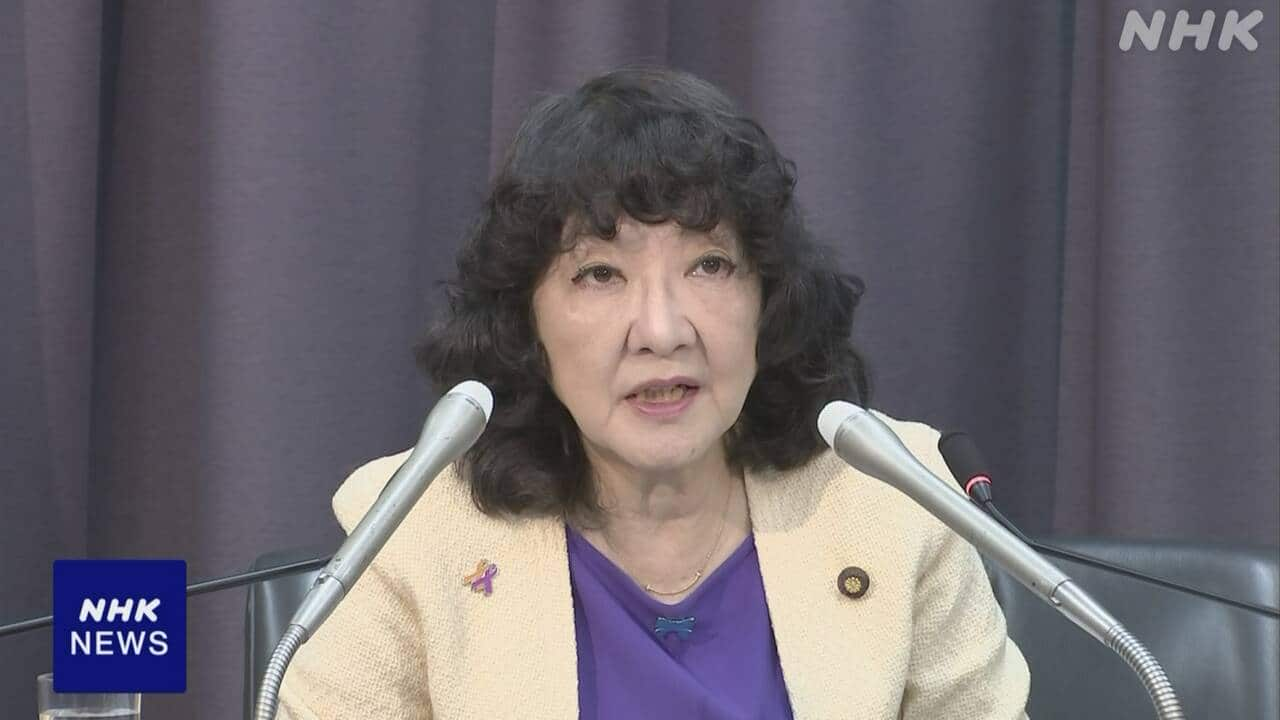和歌山県串本町にある金融機関の店長が店舗の運営資金、1億円余りを持ち出したとして業務上横領の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、串本町にある「なぎさ信用漁業協同組合連合会」の串本営業店の店長、新田博志容疑者(44)です。
警察によりますと、9月12日から16日までの間に店長を務めている店舗の金庫から運営資金の1億600万円を持ち出したとして業務上横領の疑いが持たれています。
9月16日に従業員から「金庫の金がなくなっている」と警察に通報があり、調べたところ、金庫には容疑者が書いたとみられる手紙が置かれていて、「こんな形で皆さまを裏切ることになったこと、ごめんなさい」などと記されていたということです。
警察が指名手配をして行方を捜査していたところ、19日午前1時半ごろ、東京の新宿警察署に出頭してきたため、逮捕したということです。
調べに対し、容疑を認め、「借金を返済するためだった」と話しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。