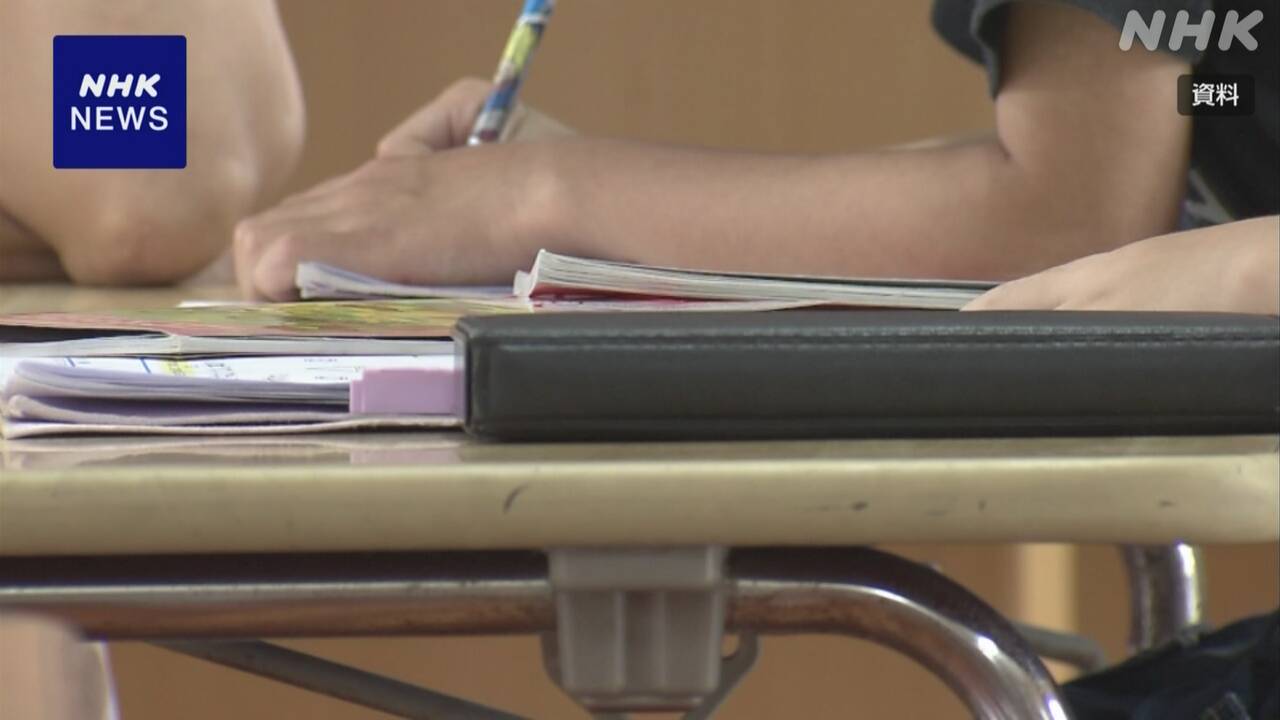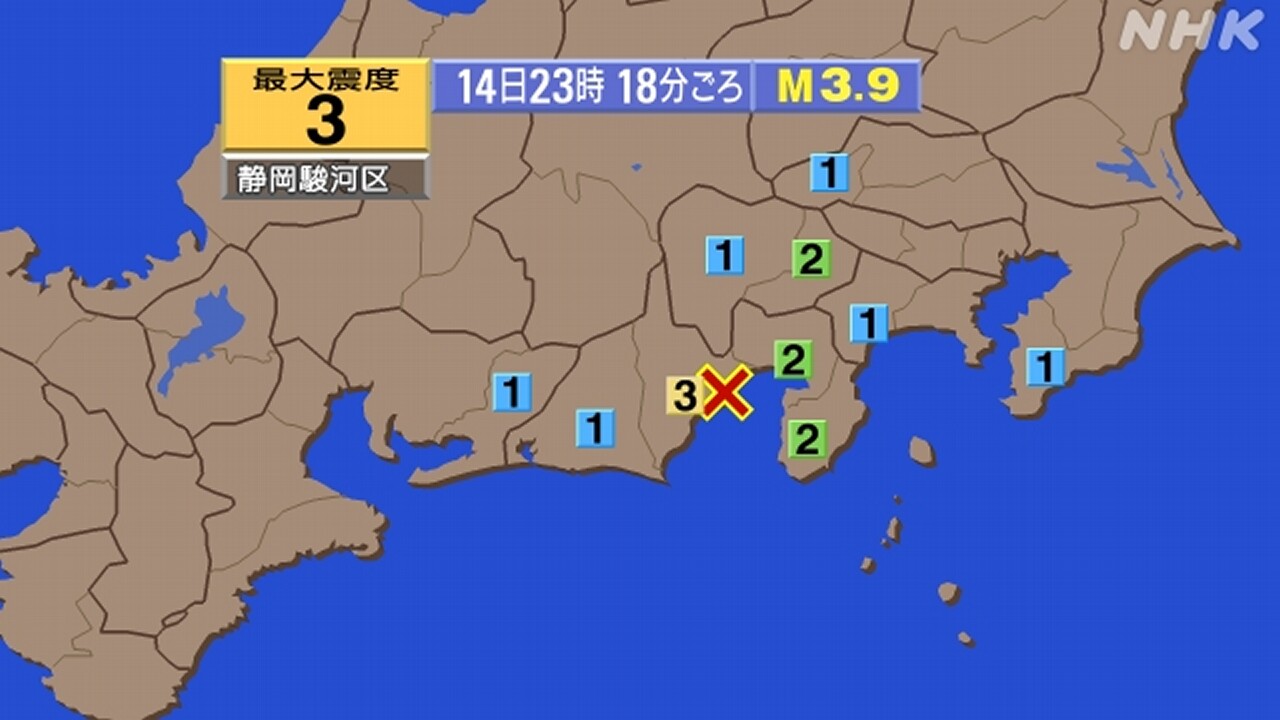共働き家庭などの小学生を放課後に預かる「学童保育」について定員に空きがないなどの理由で利用できない待機児童の数が、今年度、速報値で全国で合わせておよそ1万7000人と、4年ぶりに減少したことがこども家庭庁の調査で分かりました。
小学生が放課後の時間を過ごす「学童保育」は、共働き家庭の増加などで利用のニーズが年々増えています。
こども家庭庁の調査によりますと、今年度、学童保育を利用する児童の数は5月1日時点の速報値で156万8588人で、前の年から4万8000人余り増加し、過去最多となりました。
一方、定員に空きがないなどの理由で学童保育を利用できない待機児童の数は1万7013人と前の年と比べて673人少なくなりました。
待機児童の数が減少したのは、4年ぶりです。
都道府県別にみると、最も多かった東京都が356人減って3375人、次いで埼玉県が450人減って1682人、兵庫県が296人増えて1447人などとなっています。
青森県と福井県は待機児童がいませんでした。
学童保育を行うクラスの数は前の年と比べて全国で1000余り増えていて、こども家庭庁は、自治体への支援の拡充を進めた成果が出ているとしています。
一方で、夏休み期間中は特に利用のニーズが高まることから、こども家庭庁では夏休み期間に限定した学童保育の開所を支援するなど、さらなる受け皿の整備を後押しすることにしています。
三原こども政策相“できるかぎり市町村と連携し対策進める”

三原こども政策担当大臣は閣議のあとの記者会見で「待機児童が生じる背景には想定以上に共働き家庭が増加していることなどがある。引き続き、各自治体の実情に応じた取り組みが重要であり、さまざまな補助事業などを通じて支援していきたい。できるかぎり早期に待機児童が解消できるよう市町村と連携して対策を進めていく」と述べました。