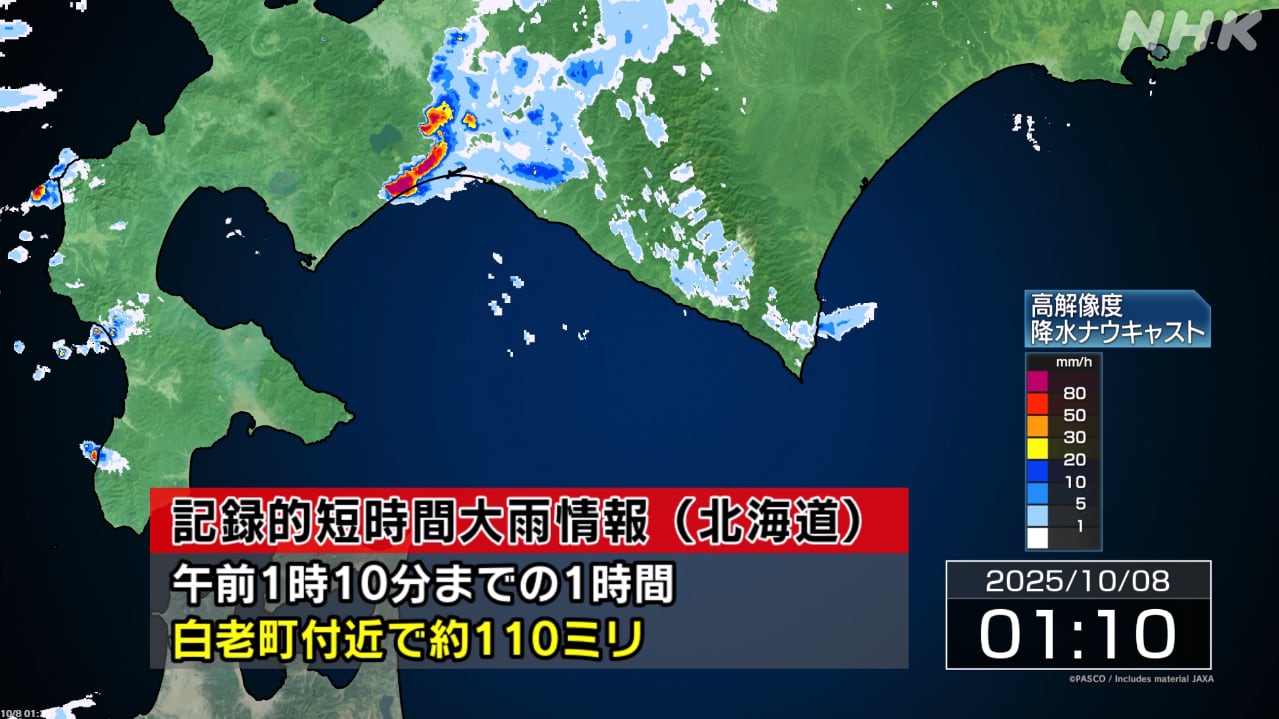殺人など重大事件の加害者が精神障害のため「責任能力がない」と判断され、不起訴や無罪になるケースがありますが、その場合、加害者に適用されるのが「医療観察制度」です。
制度開始から7月で20年。治療を通じて加害者の社会復帰が進められる一方で、被害者支援の面での課題も明らかになってきています。
医療観察制度とは
医療観察制度は、殺人や放火などの重大な事件で「心神喪失」などと判断されて不起訴や無罪となった加害者を対象に治療を経て社会復帰を進める目的で2005年7月に始まりました。
検察の申し立てに基づいて、裁判所で裁判官と医師の合議による「審判」が開かれ、医療機関に入院や通院をして治療をするかどうかなどを決定します。
厚生労働省によりますと制度開始から、おととし12月までに5100人余りが治療を受けたということです。
2001年の大阪教育大学附属池田小学校で8人の児童が殺害された事件をきっかけに医療観察法が成立しました。
知人への傷害事件で逮捕された30代男性は

7年前、知人への傷害事件で逮捕された30代の男性が取材に応じました。
男性は、傷害の罪で起訴されましたが、精神障害による「心神喪失」で責任能力がないと判断され、裁判では無罪になりました。
検察が医療観察制度にもとづく審判を申し立て、裁判官と医師の合議で入院が決まり、3年間、入院治療を受けました。
退院した現在も週に1度の通院を続けていますが、通院の際に医師の診察に加えて、心理的ケアや地域での生活を支えるスタッフとの面談もしています。
こうしたサポートについて、男性は「薬を飲まないと悪化するので服薬治療は大事だと思います。そのうえで、医師などとコミュニケーションをとるようになり、ひとの気持ちを考えられるようになりました」と話し、病気や自身の性格と向き合うことができたといいます。
一方で「退院後は、夜間や休日などに相談しにくいことなど不安もありますが、自分なりに模索しながらやっています」と話していました。
男性が通院する国立精神・神経医療研究センター病院の医師は「退院すると環境が変わり、不安だという声はある。患者本人とよく話し合いながら治療にとって良好な関係を作り、症状を自分でコントロールし、地域で暮らせるよう支援していきたい」と話しています。
被害者の妹「この制度では被害者が置き去りに」

去年7月、自宅で同居女性に刺されて死亡した芦澤正樹さん(当時42)の妹です。
逮捕された女性は精神鑑定の結果「心神喪失」と判断され「不起訴」になりました。
芦澤さんの妹は、せめて「審判」を傍聴したいと考えて裁判所に申し出ましたが、手元に届いたのは「不許可」と記載された短い通知書だけでした。

理由について詳細な説明はなく、兄の死から1年が経過した今も心の整理がつかないとして「心神喪失で不起訴になってしまうと、その罪がなかったことになって、何もなかったことのようになってしまうと感じました」と話していました。
そのうえで、医療観察制度について「この制度では被害者が置き去りになっているのではないかと感じています。加害者の方は守られて、被害者遺族の自分が叫んでも何も届かないと感じました。被害者側が意見を述べたり、何が起きたかを知ることができないので、そういうところを少しでも知ることができればいいのかなと思います」と話していました。
専門家「被害者の心情や状況を踏まえる必要がある」
この20年で刑事裁判では、被害者が意見を述べることができるようになりました。

心情を加害者に伝える制度も始まっています。
しかし、医療観察制度が適用された事件では、加害者の社会復帰の観点から、これらの制度の対象から外れていて、被害者の団体などから改善を求める声があがっています。
20年間でみえてきた医療観察制度の課題などについて、刑事政策や犯罪被害者の支援に詳しい慶應義塾大学の太田達也教授に聞きました。

審判や治療については「加害者が戻る先の社会には被害者や遺族がいるので、被害者の心情や状況を踏まえる必要がある。審判の傍聴に加えて、意見陳述や意見聴取の機会を認めることも考えるべきだ」と指摘しています。
また、太田教授は「被害者に対する共感性を養うプログラムなどを通じて被害者の心情を理解するところまで治療成果が上がる場合もある。被害者側の希望を踏まえた上で、事件や被害者に対する思いを伝える機会を設けることが、本人の社会復帰という意味でも適切な場合があると思う」としています。